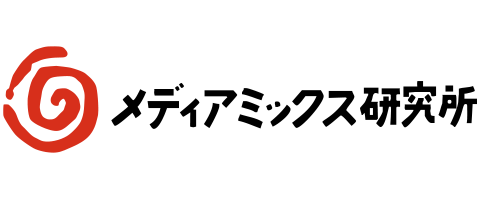報道機関としての使命を
果たすために

KSB瀬戸内海放送 報道クリエイティブユニット(高松本社)
2009年新卒入社
出身地:高知県
伊藤 佑将
災害が少ない地域だからこそ
みんなが覚悟を持ち、備えるための土台を作る
報道機関としてのKSBの司令塔
仕事内容と、どのように防災・災害報道に関わっているかを教えてください。
ニュースの現場責任者である時に、エリアの人たちに防災をより身近に感じてもらえるような情報を出したいという思いから、News Park KSB内に「こつこつ防災」というコーナーを立ち上げました。2021年4月にスタートし、いまも放送が続いています。
その後、高松本社の報道責任者になり、ニュースや情報の中身だけではなく、報道全体の体制や仕組みづくりも担う立場になりました。 災害時のシミュレーションや準備、またそれが上手く機能するかをチェックする立場でもあります。発災時には、ニュースの出し方を示すだけでなく、現場に取材に行くスタッフの安全管理や、その人たちが現場で活動するための食料や水、ガソリン燃料などの準備を含めた後方支援も行います。また、テレビ朝日系列各局との連携も担います。
災害報道では、何を伝えることを大切にしていますか?
まずは「いま何が起きているのか」ということを、早く正確に伝えることが大切です。発災直後は、どこでどんな被害が起きているのか、自治体も含めて誰もが全ての情報を把握できているわけではありません。西日本豪雨の際も、私は現場で警察や消防とお互いに情報交換をしながら取材していました。みんなで情報を拾い集めながら全体像を把握していくということが求められます。
その次の段階では、支援物資の見通しなどの生活者が知りたいことや困っていること、或いは自治体の災害対策本部が発信したい事を分かりやすく発信していくということが大切です。例えば、現場を取材していてこの地域は物資が足りないということが分かれば、それを発信して支援を呼びかけることもできますし、逆にボランティアなどの支援が受け入れられる状況にない地域であれば、それも伝えていかなければなりません。これらの情報をとにかく伝え続けるという一点につきます。
また、放送で伝えられる情報には限りがありますので、より詳しく細かい情報は、デジタルでも発信していきたいと考えています。普段から、ウェブニュース用にもどんどん記事を書こうということを進めているので、災害時にもそれを応用していきたいです。

覚悟を持ち、すぐに動けるように備える
そうした報道を行っていくために、必要な心構えは?
近年KSB で大きな災害報道を行ったのは2018年の西日本豪雨ですが、その初動がうまくいかなかったとは考えていません。ただ、油断していた部分もあります。
大事なことは、みんなが覚悟を持ちながら日々過ごすことかなと思っています。「たった今、災害が起きたらどうしよう」ということが、少しでも頭の片隅にあるかどうかです。
発災直後に、スタッフ一人一人に詳しく指示を出すことは難しいので、最初の段階では、一人一人がある程度指示がなくても動けるように、その土台を作っておかなければなりません。そのためには、日頃の啓発・訓練が必要だと考えています。
災害が少ない地域であることはありがたいことですが、だからこそ経験は少ない。本当にどれだけ覚悟をしておくかだと思っています。
経験不足を普段からどのように補うかということですね
そのために、いろいろなものの見える化を進めています。発災時にある程度オートマチックに動けるように、出社基準や緊急放送(マスターカット)の基準を簡単に1枚の紙にまとめたり、想定される仕事をフェーズや職責ごとにまとめたタイムラインを作成したりしました。実際どのように動くことになるのかを、まずはみんなに具体的にイメージしてもらうことが大切だと思い、自分の頭の整理も兼ねて作りました。報道の全員が閲覧・編集できるようにもしていて、みんなの意見を吸い上げながら更新していけばよいと考えています。
また、他の地域の災害報道を見ながら、シミュレーションをすることも大切です。「この報道は大切だ」「この報道はすべきではない」など何でもいいので、普段からどれだけ考えられているのかが、いざという時に繋がっていくと思います。
普段から信頼されるメディアになる
災害時に頼られるメディアであるために今できることは?
災害に限らず、日々の報道で信頼してもらえる存在であり続けることが大事だと思っています。そうでないと、いざという時に発信しても、それを受け取ってもらえないと思うので。いま、ウェブニュース配信に力を入れたり、SNSなどいろいろなソースから情報を得ることに力を入れたりしていますが、それらはすべて災害時にも応用できます。このエリアの中の情報を、まずKSBがしっかりと集められるようになり、その発信を続けていくことで、普段から信頼してもらえるメディアにならなければいけないと考えています。

掲載日:2025年8月4日(記載内容は掲載時点の情報です)